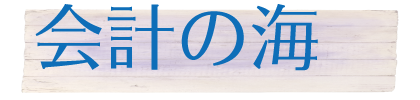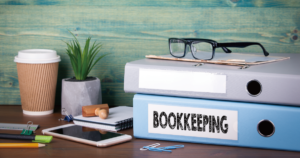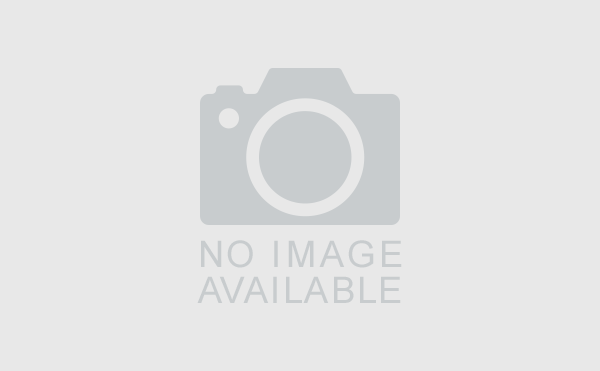【監査論】令和7年公認会計士 論文式試験 講評
厳しい暑さの中での本試験、お疲れ様でした。順次、本試験の講評を公開していきます。初回は監査論です。
出題形式は例年通り、第1問は分野横断的な理論問題、第2問は事例問題でした。答案の見当もつかないような難問はなく、「参考法令基準等」を参考にできる問題も多かったことから、解きやすかった印象です。また、「参考法令基準等」を普段から使い慣れておくことの重要性が再認識された問題でもありました。
第1問:独立性に関する分野横断的問題
「独立性」という切り口から、品質管理や報告論、制度論まで幅広く問われています。問題1、問題2の1/4、問題3、問題4の3割程度を答えられたかが目安となります。
問題1:公正不偏の態度(精神的独立性)
公正不偏の態度の保持が求められる理由の説明です。「配付法令基準等」から探せる内容ではないので、自身の頭の中にある知識で勝負です。答案は一つではないですが、標準的な受験生なら模範解答と近しい内容がアウトプットできると思います。キーワードは「公正な第三者」「監査の実施又は意見の表明の前提」「社会的制度としての監査の根底を支える最重要概念」「社会的信頼性の確保」でしょうか。外観的独立性ではなく精神的独立性が求められる理由のなので「監査の根底を支える最重要概念」は必須かと思います。
問題2:品質管理基準の独立性関連規定
品質管理基準において、独立性の確保のために監査事務所に求められる事項4つが問われました。品質管理基準は「配付法令基準等」に収録されていないので、品基報1号「監査事務所における品質管理」と監基報220「監査業務における品質管理」が多少は助けになると思います。
品質管理基準には監査事務所に求められる事項として、①独立性の保持に関する品質目標の設定、②独立性の保持に対する脅威を識別して評価、対処のための方針・手続きを定める、独立性を侵害する事項を発見、対処のための方針・手続を定める、③専門要員の独立性の適切な保持を確かめる、の3つの規定があります。②を2つに分ければ4つの事項となり答案となります。短答対策としてインプットした知識を答案にできれば理想的です。
①と遠くない規定が品基報1号-29.にあるため、独立性の保持に関する品質目標の設定について書けたかどうかがボーダーラインでしょう。②については監基報220-17.に監査責任者が監査事務所の方針・手続きを認識させる責任の規定の中に、方針・手続きの内容があるので見つけられたなら参考にできたと思います。
独立性に限らず品質管理基準は、①監査事務所が品質目標を定める、②監査事務所が方針・手続きを定める、③監査責任者が専門要員に②を遵守させる、という基本的な構成となっているので、この道筋にうまく乗せられると記述しやすかったと思います。
問題3:監査報告書の独立性関連の記載
監査報告書に監査人の独立性が記載される場所・区分を3つ指摘する問題です。監基報700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」19~.監査報告書の記載事項が列記してあるので、その中から独立性についての記載事項を探すことができます。①表題、②意見の根拠区分 が直ぐに見つけられると思います。 ③利害関係の記載は公認会計士法の規定による事項ですが、これは探さずとも思いつけた事項かと思います。
以上の記載場所・区分、記載内容に加えて、記載理由も合わせて問われていますが、こちらも①②は監基報700の適用指針に規定があるので参照できます。③利害関係の記載理由も「利害関係者の誤解を回避」「社会的信頼性の確保」といった内容で十分です。
完答も期待できる得点源としたい問題でした。
問題4:ローテーション制度
ローテーション制度の①効果2点と②実務上の弊害が問われました。①効果には、馴れ合いや自己利益といった独立性阻害要因を排除と新たな監査責任者による新たな視点の導入が指摘できます。②実務上の弊害には、知識や経験の蓄積の中断やコスト増が指摘できます。これらの内容は監査法人自体の交代の是非の論点でも成立するため、そちらから発想できたかも知れません。
比較的答案のスペースが十分用意されているので、上記内容の指摘が最低限で、どれだけ膨らませることができたかが加点となったでしょう。
第2問:グループ監査の事例問題
グループ監査に関して監査計画の策定から監査報告までが問われています。監基報600「グループ監査における特別な考慮事項」から答案の材料を探すことができるので、全体として取り組みやすい問題でした。問題1の3/4、問題2か3のどちらか、問題4の1/2、問題5を答えられたかが目安となります。
問題1:監査計画の策定
監査の作業を実施する構成単位の決定に影響を与える要因4つが問われていますが、監基報600「グループ監査における特別な考慮事項」22(1)→A51項にそのまま答案にできる規定があります。注意点として問題文中に「<資料>に照らして」との指示があるため、P社グループの具体的内容を織り込んで答案とします。買収された企業としてC社を、重要な取引種類等の分散の程度には構成比率の資料のある勘定科目を指摘する、内部統制の不備としてB社の販売プロセスを指摘するなどします。
問題2:構成単位の手続実施上の重要性の決定プロセス
構成単位の手続実施上の重要性を決定する3つのプロセスを直接規定している項が監基報600にないので、案外答えにくかったと思います。答案としてはグループ監査における重要性の関係性から、①グループ財務諸表全体の重要性の基準値→②①より低い金額としてグループ・レベルの手続実施上の重要性→③②より低い金額として構成単位の手続実施上の重要性 の3つを決定プロセスとして説明できます。加えて、合算リスクを適切な低い水準に抑えるためであることを指摘できれば完璧です。「一般に」とあるので、事例を織り込む必要はありません。
問題3:構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項
構成単位の監査人の作業に十分かつ適切に関与できるかどうかの評価については、本問の場合、C社が海外子会社である事とその監査人Zがいずれのネットワーク・ファームにも属していない点を答案に反映できたかがポイントです。
構成単位の監査人が関与する場合の考慮事項として監基報600-23.→A57項に構成単位の監査人とのコミュニケーションに関して監査調書の共有を含むコミュニケーションの制約の有無や言語の問題が指摘されているので、この規定さえ見つけられれば適切な答案にできたと思います。
問題4:虚偽表示の識別
問1:コミュニケーションを行う金額の基準値の決定プロセス
構成単位の財務情報において識別された虚偽表示についてグループ監査人とコミュニケーションを行う金額の基準値は、グループ財務諸表にとって明らかに僅少と考えられる金額を超えてはならない と規定されていますから(監基報600-35項(2))、「~を超えないように決定する」で十分な答案です。答案スペースが数行もあるので、A121項まで手を広げると明らかに僅少と考えられる金額の説明があるのでそこまで書き出せると完璧です。
問2:虚偽表示が修正済みでもコミュニケーションが要請される理由
修正済みの虚偽表示についてもコミュニケーションが要請されるとの規定は、コミュニケーションが要請される11項目の1つとして規定されているので(監基報600-45項(5) )、若干見つけにくさがある印象ですが、ここからA145項をたどれればそのまま答案にできる規定になっています。
監基報から探せなかった場合でも、虚偽表示は単独で発生するとは限らないとの知識から、類似の虚偽表示や内部統制の不備を示唆している可能性について指摘できたなら良かったと思います。
問題5:グループ監査報告
問1:グループ財務諸表に対する監査報告書において構成単位の監査人の利用について言及してはならない理由
「一般に」とあるので、典型論点として用意しておいた答案を書き出せれば十分です。グループ監査人と構成単位の監査人との間で責任の限定も分担もない旨や、監査報告利用者の誤解を回避すべき旨ですね。
問2:構成単位の監査人が要請された作業を完了できなかった結果、構成単位の財務情報に関して十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、グループ財務諸表に対して限定付適正意見を表明することとなった場合に、グループ財務諸表に対する監査報告書において構成単位の監査人の利用について言及することの是非
問1同様に典型論点として用意しておいた答案を書き出すことになりますが、①問2は事例を踏まえた解答が要求されているので、監査人Y、B社への言及、②問1で答えた理由に関連づけること、③是非が問われているので「是」であるとの結論、の3点は最低限意識して答案にします。問題文中に「B社の経営者の管理の及ばない状況により」とあるので、経営者への働きかけについての言及は不要です。
典型論点だからこそ、①~③のような問題に寄り添った答案にできるかで差が出ると思います。
以上です。