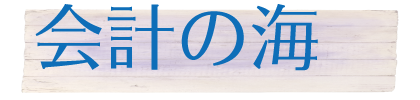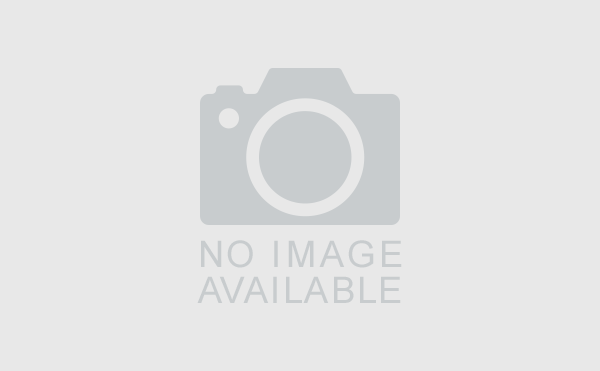【会計学(午後)】令和7年公認会計士 論文式試験 講評
会計学(午後)財務会計論の講評です。
第3問
例年通り、個別論点の計算問題と関連する理論問題の出題形式でした。今回は問題1:株主資本等変動計算書、問題2:中間財務諸表からの出題でした。
問題1:株主資本等変動計算書
問1:計算は株主資本等変動計算書の8箇所の数値の算定です。個々の会計処理はさほど難しくはないのですが、8箇所の内6箇所が合計欄ということもあり、当初の印象以上の解き難さを感じました。以下、幾つか注意点を指摘して行きます。
- 新株予約権付社債は区分法により処理するとあるので、新株予約権の対価12,000が取得差額となり償却原価法の定額法の対象となります。
- 中間配当時に利益準備金を配当額の1/10積み立てますが、その際、資本金の1/4規制は当然考慮したと思います。本問の場合、中間配当の基準日までに新株予約権付社債の権利行使により資本金が増加し、その1/4の額も増加しています。この点を見落とすと③利益準備金の変動額を間違えてしまいます。
- その他有価証券評価差額金の増減額を内訳まで要求されています。ただし⑥純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増減は差額で求めることができるので、「期首7,560△売却した30%分の取得から売却までのその他有価証券評価差額金3,780+⑥=期末その他有価証券評価差額金10,010」が成り立つように⑥を求めます。
- ヘッジの消滅は繰り延べてきたヘッジ損益84,000を損益認識するだけです。為替予約の原則的なヘッジ会計の方法は繰延処理なので、時価評価差額を繰延ヘッジ損益とします。145円/$のドル買い為替予約を締結し、期末為替相場150円/$ですから為替差益の繰延になります。
問2:理論は(1)株主資本等変動計算書が必要とされる理由、(2)株主資本と株主資本以外で表示方法に差異がある理由 が問われました。どちらも典型論点なので答案の用意はあったかと思いますが、(1)の「会社法の計算規定と関連させて説明」との指示をどう解釈するかが難しかったでしょう。用意した答案は「その他有価証券評価差額金などの純資産の部に直接計上される項目が増加した」「株主資本の変動要因が増加した」ことを理由として挙げていると思いますが、「会社法の計算規定と関連させて説明」では前者の理由は当てはまらないので、後者について会社法上許されている点を指摘することになります。この点の難しさから、(2)を優先して記述するが吉でした。
以上より、問題1は計算・理論共に1/2が目安かと思います。
問題2:中間財務諸表
金商法の四半期開示制度の改正をうけての中間財務諸表からの出題です。問1:計算は〔資料Ⅲ〕に処理の結果を書き足していけば良く、見た目より簡単に解くことができました。計算は10箇所中8箇所まで楽々解けたでしょう。税金費用の簡便な計算についてだけは対策していないと手こずったかも知れませんがそう難しくはありません。
- リベートについて、収益の著しい減額が見込まれるときは収益認識しないので、売上高420,000の3%は売上高からのマイナスとします。
- 破産更生債権等の貸倒引当金の設定において、担保処分等に相殺適状な買掛金を含め忘れないよう注意します。
- 原価差異の中間特有の処理では、売上原価として処理している差異をその他の流動資産(借方差異)に振替とします。
- 税金費用の計算では、予想税金費用175,000(=(税引前利益700,000+永久差異60,000)×30%ー税額控除53,000)を税引前利益700,000で割ると実効税率0.25を見積もることができます。
問2:実績主義と予測主義の論点です。四半期財務諸表から引き継いだ典型論点ですし、答案の用意があったと思います。
問3:繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり簡便的な取扱いが認められている理由についても、答案の用意があったと思います。
直近の改正があったこと、他の論点に比べて重視されない分野である事、会計士試験の受験生は連結会計以外の総合問題を解き慣れていない事を勘案すると、計算は8/10、理論は2/4が目安かと思います。
第4問
第4問は理論のみから計算も含む出題へ出題形式が変化してきて、今回も少しだけ計算要素が含まれていました。全体として答案を用意できている問題が多かった印象ですから、受験生の努力が報われるタイプの良問だと思います。
問題1:ストック・オプション
問1:本源的価値と時間的価値の理解
一読して何を問われてるか直ぐに分かりましたか?ストック・オプションの公正価値の内、本源的価値はその時点で権利行使した場合の価値なので、付与日の価値は△500(=株価7,500ー行使価格8,000)、決算日の価値は1,000(=株価9,000ー行使価格8,000)です。一方、時間的価値は株価変動への期待なので時間の経過と共に減少する性質をもつため、付与日の方が大きくなります。
問2:公正な評価単価を見直さない理由
典型論点として用意した答案があったと思います。企業と従業員との間の条件付の交換契約が付与日時点における等価交換で成立していると考え、その後の株価の変動による公正な評価単価の変動は交換されたサービスの価値とは無関係なため、見直し不要とされます。
問3:オプション数の変動と会計処理
権利不行使によるオプション数の変動と条件変更によるオプション数の変動で会計処理が異なる理由が問われています。「基準」7項と11項を参照するよう求められる珍しい形式の出題でした。両者は企業が意図したオプション数の変更か否かが異なります。条件変更によって企業が意図したオプション数の変更は将来にわたる効果を期待してのものなので将来(残存期間)に影響させる処理となっています。
問1の出題意図が読み取りにくい気がしますが、少なくとも問2と問3は得点源にできたはずです。
問題2:退職給付会計
問1:遅延処理の理由
典型論点として用意した答案があったと思います。一時の費用とせずに遅延処理する理由なので、数理計算上の差異は予測数値の修正も反映されること、過去勤務費用は勤労意欲が将来にわたって向上するとの期待によること がキーフレーズになります。
問2:費用処理期間
(1)費用処理期間を一定年数に継続適用する理由は、継続適用のすべてに共通する期間比較可能性の確保です。(2)平均残存勤務期間の見直しの場面は、平均残存勤務期間自体がどう算定されるかを考えると思いつけたかも知れません。
問3:過去勤務費用の発生する場面と算定方法
計算の指示になっていることも多いので近しい内容が書けたと思います。
問1を確実に記述して、問3もできれば書けてほしいところです。
問題3:満期保有債券
問1:満期保有目的債券の要件
企業側の保有意図(意思と能力)ではなく、対象となる債券が備えるべき要件なので償還日の定めと額面償還の予定が解答になります。
問2:償却原価法(利息法)の計算
(1)実効利子率は、将来CF(社債利息1,000×2年と額面償還100,000)の割引価値が取得価額98,062に一致する割引率です。1年後のCF1,000の割引価値は与えられた現価係数表から平均で985位ですから、(98,062ー985)÷2年後のCF101,000=0.96115…となるので、2年目の現価係数が0.9612の2%と推定できます。(2)決算日の仕訳は(1)の実効利子率さえ求められたなら簡単だったはずです。
問3:転換社債型新株予約権付社債
(1)転換社債型新株予約権付社債が満期保有目的になじまない理由は、転換社債型は権利行使により社債払込することを想定=額面償還を想定しない からです。(2)(1)より転換が想定されない状況、新株予約権の権利行使が不利な状況を指摘すればいいと分かります。
問1と問2は正答したい問題でした。
問題4:固定資産の貸借対照表価額
問1:資産の測定
概念フレームワークの資産の測定値に関する記述の空欄補充です。①市場価格は「購買市場と売却市場とが区別」から明らかなので、残る②が割引価値であると分かります。
問2:交換による取得原価
交換による取得では(1)同一種類かつ同一用途か(2)それ以外かで取得資産の取得原価が異なります。(1)同一種類かつ同一用途の場合には投資は継続していると考えて譲渡資産の適正な簿価で譲受資産を引き継ぎ、(2)それ以外の場合には投資は精算(時価で売却)して新たな投資を開始したと考え譲渡資産の時価=売却額での譲受資産の取得とします。
問3:投資不動産
我が国では投資不動産は賃貸等不動産に含まれ、時価を注記するのみで時価評価しません。その理由として、時価の客観的な把握は一般に困難であること、事実上は事業投資である場合がある事、整備された単一の市場が存在しない事など、直ちに売買・換金を行うことに事業遂行上等の制約がある事が指摘できます。答案の用意があっても良い典型論点ですが、投資不動産自体が受験上重視されない分野なので、準備できていた場合はアドバンテージだったかも知れません。
これも問1と問2は正答したい問題でした。
第5問
第5問は、例年通り、連結会計からの出題でした。
計算の解答箇所は18箇所、理論は250字×2問+350字×1問の3問でした。
計算の難易度別の出題比率は、Cランクの問題が44%、Aランクの問題が39%、Bランクの問題が17%でした。
Cランクからの出題が最も多かったので、難しい印象でしたが、例年通り、Cランクは捨てて、AランクとBランクの問題だけを解いておけば大丈夫です。
理論は、3問ともAランクでした。以下では、「正答しておけば合格ラインに到達できる問題」を中心に、計算過程を示しておきます。
短答受験生も是非、チェックしてみて下さい。
問題1:ストック・オプション
問1:連結B/Sの作成
連結子会社は2社で、税効果会計が適用される問題でした。
処理量が多く、連結修正仕訳を下書きに並べていては、時間が足りなくなるので、正答できそうな箇所をピンポイントで拾っていくのが賢明です。
主な論点は、以下の通りです。
A社(70%子会社): 過去に段階取得、アップストリームの成果連結、第三社割当増資
B社(60%子会社): 過去に一部売却、ダウンストリームの成果連結、親子間での資金の貸借
本問はCランクの問題が多いため、正答できそうな箇所を一通り済ませてから、時間があれば、Bランクの問題にも手を広げていくイメージです。
問1では、連結のB/S項目が8つ問われているので、まず、手を出さない方が無難な問いを幾つか選んでから解き始めるのが良いです。
①繰延税金資産、⑦資本剰余金、⑧非支配株主持分は手を付けずに、残りの5問のうち、4問の正答を目指す方針です。
実際に解き始めてみると、③建物、⑤買掛金、⑥長期借入金は簡単なので、あとは、②の土地と④の「のれん」のいずれか一方、若しくは両方の正答を目指します。
②の土地(Bランク)
個別会計上の土地のB/S価額合計は112,600千円です。A社は土地の40%をP社に売却しているので、評価差額分3,000×60%=1,800千円が当期末連結B/S土地に計上されるので、加算します。P社土地の個別会計上の金額には、A社から購入した土地に係る未実現利益800千円が含まれているので、これを控除します。個別会計上の売却益は2,000千円ですが、このうち、A社が土地を取得した日から支配獲得日までの値上益1,200千円は実現したと考えるので、土地勘定から控除すべき未実現利益は800千円とします。あとは、B社が土地を取得した日から支配獲得日までに評価損が1,000千円発生しているので、これを控除します。
P社48,600+A社30,000+B社34,000+A社土地の評価差額(53,000-50,000)×60% - P社保有土地に含まれる未実現利益(22,000-53,000×売却割合40%)-B社土地の評価差額(34,000-33,000)= 112,600千円
④の「のれん」(Aランク)
B社は「負ののれん」となるので、A社の「のれん」のみ計算過程を示しておきます。
A社への投資額74,400千円×(70%/60%)-A社の純資産額(60,000+18,000+24,000+評価差額3,000×70%)=13,930千円
∴ 13,930千円×9年/10年= 12,537千円
問2:連結P/Lの作成
連結P/Lについては、4箇所問われています。
⑪の法人税等調整額と⑫非支配株主に帰属する当期純利益は、難しそうなので、⑨の売上原価と⑩の販売費及び一般管理費合計の2箇所を正答できれば、十分です。
⑨の売上原価
P社382,000+A社314,000+B社295,000-AP間販売20,000+未実現利益2,000×0.25=971,500千円
⑩の販売費及び一般管理費
P社140,200+A社92,200+B社86,800-貸倒引当金繰入額3,000×0.02+減価償却費(23,000÷20年×8年-8,400)÷8年+のれん償却1,393=320,633千円
問3:連結株主資本等変動計算書の作成
連結S/Sについては、2箇所問われています。
⑬の利益剰余金等期首残高は捨てて、⑭の非支配株主持分当期首残高に集中します。
⑭の非支配株主持分当期首残高
A社の期首純資産額(60,000+18,000+24,000+評価差額3,000×70%)×30%+B社の期首純資産額(50,000+23,000+16,500-評価差額1,000×70%)×20%=48,990千円
問4:連結キャッシュフロー計算書の作成(間接法)
連結C/Fについては、4箇所問われています。
⑮の税金等調整前当期純利益を捨てて、⑯の受取利息及び受取配当金と、⑱の利息の支払額を正答できれば、十分です。
⑯の受取利息及び受取配当金
P社1,480+A社580+B社280-P社B社間の利息30,000×2%×4/12=2,140千円 → △2,140千円
⑱の利息の支払額
P社400+A社1,200+B社500-P社B社間の利息30,000×2%×4/12-未払増加額{(当期末未払300-PB間未払200)-前期末未払400}=2,200千円 → △2,200千円
解答箇所が18箇所です。そのうち、②③④⑤⑥⑨⑩⑭⑯⑱の10箇所は正答して欲しいですが、②⑱は少し難しいので、合格ラインは8~9箇所としておきます。
問題2:理論(250字×2問+300字×1問)
問1:子会社の欠損金(250字)
理論講義で取り扱っている典型論点なので、以下の内容を字数オーバーにならないよう答案に反映させておけば、大丈夫な問題です。
⇒ 本来株主は、株主有限責任の原則により、出資額を限度とする責任を負うのみですが、親会社は、例えば、子会社に対する保証債務契約に基づく責任を負ったり、子会社に対する経営責任により子会社債務を肩代わりするなど、子会社の債権者に対して、出資額以上の責任を負うのが一般的です。
⇒ 親会社が出資額以上の責任を負うのであれば、子会社に欠損金が生じた場合に、非支配株主には出資額を限度とする責任しか負わせる必要はありません。
⇒ 非支配株主が出資額を限度とする責任しか負わないということは、「子会社の欠損金額のうち、非支配株主の持分割合に相当する分」が「当該非支配株主の出資額」を超えている場合、その超過額は、非支配株主ではなく、親会社が負担することになります。
問2:一部売却時における「のれん」未償却額の会計処理(250字)
計算知識を思い出しながら、次の3つのケースに区別して解答しておけば、合格ラインに到達します。
(1) 一部売却しても、支配関係が継続するケース ⇒ 「のれん」の未償却額は減額しない
(2) 一部売却により、関連会社となるケース ⇒ 「のれん」の未償却額のうち、売却分は取り崩し、残存分は投資評価額の算定に含める
(3) 連結除外となるケース ⇒ 「のれん」の未償却額を全額取り崩す
問3:持分法適用会社との間で生じた未実現損益の消去方法(300字)
計算の指示に従って、(1) アップストリームの場合と、(2) ダウンストリームの場合に分けて解答します。
本問も計算知識で解答可能です。
(1) アップストリームの場合
未実現損益に持分比率を乗じた金額を未実現損益が含まれる投資会社の資産の額に加減するとともに、同額の投資損益を計上する
【仕訳例】(借)持分法による投資損益 ××× / (貸)商品 ×××
(2) ダウンストリームの場合
未実現損益に持分比率を乗じた金額を被投資会社に対する持分相当額に加減するとともに、同額だけ投資会社の売上高等を加減する
【仕訳例】(借)売上 ××× / (貸)A社株式 ×××
以上になります。