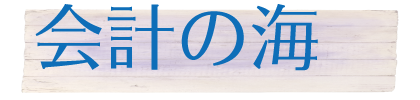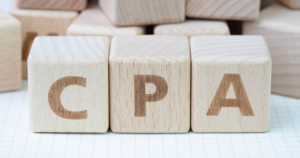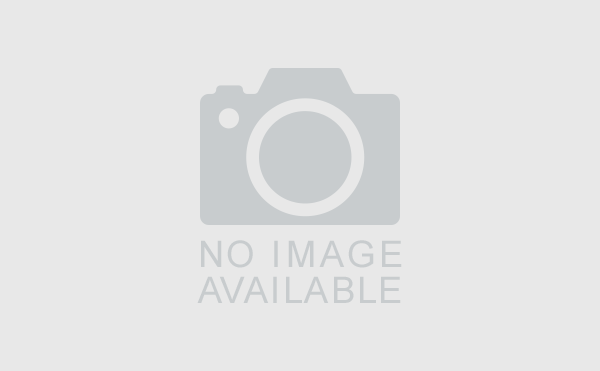【会計学(午前)】令和7年公認会計士 論文式試験 講評
本試験、お疲れ様でした。今回は管理会計論です。
出題形式は例年通り、30分問題×4問でした。
問題の指示に忠実に従った仕損費の処理や、試行錯誤が要求されるセールスミックスの決定など、油断ならない問題も含まれていましたが、全体としては、易しかった印象です。
第1問:
問題1が「総合原価計算 ~ 仕損費の処理」、問題2が「標準原価計算 ~ 配合差異・歩留差異」というオーソドックスな分野からの出題でした。
問題1:総合原価計算 ~ 仕損費の処理
「先入先出法」、「非度外視法」、「製品検査点が2箇所」という条件の下での総合原価計算の問題でした。
短答式試験では、正常仕損品と異常仕損品の数量は、資料に与えられることが多いですが、本問では、「7月における40%検査点で合格した数量に対して4%までは正常仕損品であり、・・・」、「100%検査点で合格した数量に対して2%までが正常仕損品である」という指示に従って、自分で計算する必要がありました。こういったところから、非度外視法の問題であっても、「短答式の問題よりも難易度はワンランク上」といった印象を受けます。
期首仕掛品は6月中に40%検査点を通過しているので、7月に、40%検査点で検査を受けたのは5,000個で、そのうち4,750個が良品、250個が仕損品でした。
なので、4,750個×4%=190個が正常仕損品で、残りの60個が異常仕損品です。
40%検査点を通過した4,750個のうち、500個は60%の期末仕掛品となったので、当月中に100%点にたどり着いたのは、4,250個(=4,750個-500個)。
この他にも、期首仕掛品700個(50%)も当月中に100%点にたどり着いています。
従って、4,950個(=4,250個+700個)が100%点で検査を受けて、100個が不良品と判定され、残りの4,850個が「100%検査点で合格した数量」ということになります。なので、4,850個×2%=97個が正常仕損品で、残りの3個(=100個-97個)が異常仕損品です。
40%検査点の仕損品250個は正常190個、異常60個で、100%検査点の仕損品100個は正常97個、異常3個。
これらの数量の把握ができれば、計算は全て正答できたはずです。
あとは、理論です。
問5では、定点発生を前提に、度外視法と非度外視法の計算結果が異なる理由が問われました。
定点発生の場合には、加工費の計算結果が度外視法と非度外視法とで異なるという論点は、短答知識の範囲内です。
ここまでで確認したように、本問の計算条件では、度外視法と非度外視法の計算結果は異なるわけですが、それでも、度外視法と非度外視法の計算結果を一致させるためには、原価計算方式をどのように変更すれば良いのかが、問6で問われました。これも、「完成品のみ負担」の場合に、両計算方法の結果が一致することは、よく知られた論点なので、保守主義の観点から完成品のみ負担に変更すれば良い、といった内容を答えておけば十分です。
問題2:標準原価計算 ~ 配合差異、歩留差異
「1ダース=12個」ということを知らなければ、手も足も出ない問題です。
私の世代は、子供の頃に鉛筆を1ダース12本で購入していたので、本問でも、「1ダース=12缶」として解くことができました。
あと、普段生活をしていて、「1ダース」という単位を使うのは、ゴルフボールくらいでしょうか?
少し心配になって、息子に「1ダースって、何個か知ってる?」と尋ねたら、「12個」と即答したので、案外、大丈夫なのかもしれません。この点がクリアできれば、材料に関する配合差異・歩留差異の分析は難しくはなかったはずです。
ただ、解きにくいように、資料は故意に整理整頓されていません。〔資料1〕に完成品が18ℓ/缶とありますが、標準材料投入量a10ℓ、b5ℓ、c5ℓは〔資料4〕まで読み進む必要がありました。この2つの資料から、本問の標準的な投入産出関係は、「20ℓ(=a10ℓ+b5ℓ+c5ℓ)を投入して、2ℓ減損して、完成品が18ℓ」ということになります。短答式なら、このあたりの資料が整理整頓されていて、1箇所にまとめてくれています。
この標準的な投入産出関係が分かれば、実際の完成量が38ダース=12×38=456缶なので、各原料のSQや、配合差異・歩留差異を計算するためのS’Qの算定も難しくないです。
問3の加重平均価格を利用した配合差異・歩留差異の計算は、典型的な短答対策論点です。
問4は、問2、問3の計算結果をまとめる理論です。
相対的に安価なC原料を多くの割合で投入しているため、配合差異は当然に有利差異となります(問3の加重平均価格を利用した配合差異の計算結果より)。
一方、安価な材料を多くの割合で投入した場合、減損発生率が高くなるのが一般的ですが、本問では、原料全体での歩留差異も有利差異となっています(問2の歩留差異合計)。ただ、解答スペースが2行しかないので、前半の配合差異の記述だけで大丈夫なはずです。
問5は、加工費差異に関する問題ですが、月間の稼働日数が(エ:20)日と予定されている、という(エ)の空欄が難しかったです。
難しかったのは、問題文に舌足らずな箇所があったからで、〔資料2〕2段落目です。
「加工を開始したら途中で止めることができず,加工完了後は,その都度,釜を洗浄し,同じ日に再び機械を稼働させることはない。」とありますが、この「加工完了後は」というところは、「1ロットの加工完了後は」としておいて欲しかったですね。
そうすれば、「1日あたり1ロットしか生産しない」ことが明確になるので、月間の稼働日数が(エ:20)日が簡単に計算できます。
「月間の予定機械時間100時間」を「1ロットあたり機械時間5時間」で割って、「月間の予定生産量20ロット」です。
「1ロット生産するのに1日かかる」のなら、「月間の予定稼働日数は(エ:20日)」となりますよね。
基準操業度20日(=100時間)通りに操業すれば、固定加工費がピッタリ製品原価処理されるように固定費率を設定しているのに、現実には、19日(∵ 実際生産量38ロット)しか稼働していないので、1日(=2ロット=5h)分だけ固定加工費の配賦不足(不利差異)が生じているはずです。これが3分法の2による、「あるべき本来の操業度差異」です。本来、操業度差異は5h分の不利差異とされるべきです(⇒3分法の2では、そのような計算を行っている)。
ところが、本問では、固定費からも能率差異を計算するという3分法の1による差異分析を行ってしまっているので、本来、固定製造間接費の配賦過不足額を意味するものとして、5h分の不利な操業度差異として把握すべきところ、その5hの不利差異を、「3h分の有利な操業度差異」と「8h分の不利な固定費能率差異」としてしまっています。
このようなことが理解できているのかを確認したくて出題したと思われますが、このあたりは、「管理会計論マニア向けの論点」ということになるので、パスしても大丈夫です。
第2問:
問題1が「営業利益の予算実績差異分析」、問題2が「最適セールス・ミックスの決定」からの出題でした。
例年、第2問の方が難しいですが、今年度は、第2問の方が易しく感じた受験生も多かったと思います。
問題1:営業利益の予算実績差異分析
営業利益の予算実績差異分析は、論文式試験で過去に何度も出題されている論点ですが、計算については、差異分析のボックス図に、資料の数値をあてはめるだけで、必ず解けます。本問も例に漏れず、短答知識だけで完答できるレベルの問題でした。
問2では、「今後、急成長すると予測される市場に今年度より投入されたA製品について、積極的な販売活動を進める上で、目先の目標営業利益の達成のみを重視すべきではない。」とされる理由が問われています。誘導型の問題なので、解きやすいですね。
問題文の「積極的な販売活動」というヒントを利用して、「積極的な販売活動」すなわち、広告宣伝費をたっぷりと投入すると、どうなるかを考えます。
広告宣伝費をたっぷり投入すると、コストが先行してしまうので、短期的には目標の営業利益は達成できない可能性が高いです。ただ、目先の利益を優先して、販売活動に消極的になってしまうと、今後、急成長が予想される市場に乗り遅れてしまうため、目先の目標営業利益の達成のみを重視するのは適切ではない、といった内容が書けていれば大丈夫です。
問3は、経理課長が行った差異分析を推定する問題です。
〔会話〕から、製品Bについては、「販売活動に係る不利差異」よりも、「製造活動に係る有利差異」の方が金額が大きいことから、全体として、「有利な営業利益差異」が生じている、という展開になります。営業利益の予実分析の方法には、ご存じの通り、項目別分析と要因別分析とがあります。
| 売上高差異 | 変動販売費差異 | 固定販売費差異 | 変動製造原価差異 | 固定製造間接費差異 | |
| 項目別分析 | △ 2,600千円 | △ 620千円 | △ 1,000千円 | + 4,280千円 | + 1,000千円 |
| 要因別分析 | △ 890千円 | △ 780千円 | △ 1,000千円 | + 2,730千円 | + 1,000千円 |
TACの解答速報は「項目別分析」です。これに対して、CPAの解答速報は、売上高差異を項目別分析の△2,600千円としつつ、販売活動に関する差異を△2,670千円、製造活動に関する差異を+3,730千円としているので、要因別分析の計算結果に一致させるような形をとっています。
管理上、望ましいのは、要因別分析です。なので、多くの受験生が「販売活動に関する差異」を△2,670千円(=△890+△780+△1,000)、製造活動に関する差異を+3,730千円(=2730+1,000)と答えたはずです。当然、正解になりますが、作問者は、「経理課長はどのような分析を実施したと考えられるであろうか。」という推定問題として作問してしまっているので、項目別分析による解答も正解とせざるを得ないはずです。採点が大変ですね。
問4の理論問題は、「原価標準を高めに設定するとどうなるの?」といった内容です。
当然、適正な原価標準を設定している時よりも、製造課では有利な製造原価差異が計上されてしまうため、製造課の業績が過大に好評価とされる、ということですよね。
問5は、「貢献利益に与えた影響を分析」とあるので、要因別分析による販売数量差異を「市場占有率差異」と「総需要量差異」に分解して、総需要量が減退したことによって失った貢献利益の金額と、市場占有率を予算の25%から実績の26%に向上させたことによって獲得した貢献利益の金額を解答することになります。
問題2:最適セールス・ミックスの決定
製品Aの生産販売量は確定していて、残された生産能力のもとで、製品Bと製品Cのセールスミックスについて検討する問題です。
共通する制約条件が機械作業時間のみなので、グラフを作成する必要もなく、簡単に解けるはずです。
ただ、Bの生産販売量が 595MH÷0.3MH/個=1,983.333…個と計算されて、きれいに割り切れません。セールス・ミックスの決定問題では、きれいに割り切れない時点で、試行錯誤が必須の手順となるため、(B、C)=(1,983個、9,600個)の貢献利益だけでなく、(B、C)=(1,984個、9,599個)が成立するのか、成立しなければ、(B、C)=(1,984個、9,598個)あたりまで手を広げて、最適セールス・ミックスを探る必要があります。
設問2は、「追加で製品Bだけを生産販売した場合と、製品Cだけを生産販売した場合の営業利益の差額を「差額原価収益分析」を行うことによって計算しなさい。」という問題ですが、設問1の段階で、製品Cだけをの方が営業利益が90,700千円多いという結論は計算済みです。
なので、「差額原価収益分析による計算過程」を記述する問題です。
TACの解答速報は、「製品Aを生産販売している状況を基準に、製品Bを追加で生産販売すると収益と原価と利益がいくら増加して、製品Cをを追加で生産販売すると収益と原価と利益がいくら増加するので、両者の利益を比較して、結局、製品Cだけを追加で生産販売した方が営業利益がいくら多くなる。」といった展開になっています。
これに対して、CPAの解答速報は、「製品Aを生産販売している状況を基準に、製品Bを追加で生産販売すると利益がいくら増加して、製品Cを追加で生産販売すると利益がいくら増加するので、両者の利益を比較して、結局、製品Cだけを追加で生産販売した方が営業利益がいくら多くなる。」といった展開なので、差額利益だけを取り出して解答しています。
本問は「差額収益分析を行いなさい。」という問題なので、「追加で製品Bだけを生産販売するよりも、製品Cだけを生産販売した方が売上高がいくら増加して、原価がいくら増加して、従って、利益がいくら増加する。」といった展開も考えられます。
いずれも正解とすべきなので、採点が大変な問題を出題してしまった印象です。
設問3は、先述した、Bの生産販売量が 595MH÷0.3MH/個=1,983.333…個と計算されて、きれいに割り切れないため、製品Bと製品Cの最適セールス・ミックスの決定には、一定の試行錯誤が必要となる、といったことが理解できていれば、正答できる内容です。
設問4は、内部失敗コスト(内部失敗原価)と外部失敗コスト(外部失敗原価)という語句を記述させる問題です。短答知識ですね。
設問5は、「設計段階で行うべき品質原価を抑制する取り組みを2つあげなさい。」といった問題なので、その場で考える問題です。
本来であれば、「内部失敗原価を抑制する取り組み」と「外部失敗原価を抑制する取り組み」をそれぞれ1つずつ解答するのが模範的な解答となりますが、前者の「仕損費を抑制する取り組み」について解答する方が簡単そうです。
例えば、設計段階で、良質な材料を取り入れる、部品点数を減らす、工数を減らす、機械化を促進する、色々と思いつきそうですね。
以上です。