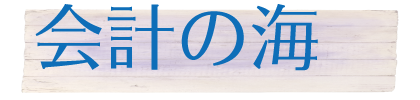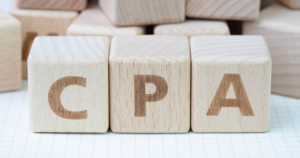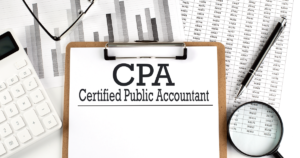【租税法】令和7年公認会計士 論文式試験 講評
本試験、お疲れ様でした。今回は、租税法の講評です。
理論40点、計算60点というのは例年通りで、配点は、法人税法52点(理論22点+計算30点)、所得税法23点(理論9点+計算14点)、消費税法(理論9点+計算16点)でした。
次に、難易度ですが、理論は、得点に差がつきにくい内容でした。
9問中2問は没問で、Aランク3問、Bランク4問という構成でしたので、没問2問は白紙、残りの7問は持っている知識で答案用紙を埋めておけば、合格圏内の大集団の中に残れたはずです。
計算は、相変わらず所得税法が難しかったですね。
正答しておきたい問題は、法人税法は15問中8問、所得税法は7問中3問、消費税法は8問中6問で、全体では30問中17問です。
第1問:理論(40点)
問題1が記述問題で@5点×4問=20点、問題2が正誤問題で@4点×5問=20点というのは例年通りです。
基本方針としては、計算知識で解ける問題を優先して解答する、ということですが、適切な条文を指摘できるかが得点に大きく影響するので、日頃から条文に触れる習慣をつけておく必要があります。学習意欲の湧かない日は、租税法や企業法の条文をペラペラめくりながら、ぼんやり眺める、というのがおすすめです。
問題1:
問1:A~所得税法【非適格ストックオプション~個人側】
令和6年7 月4 日,P はA 社に対して上記新株予約権1,000個を行使して,1,000万円を払い込んで,A 社株式1,000株を取得した。同日のA 社株式の1株当たりの時価は,2万円であった。なお,P は,A 社から令和6年中に月額100万円の役員給与を受け取っており、他に収入はない(事実①)。
問い:事実①に関して,所得税法上,P の令和6年分の総所得金額に算入すべき金額はいくらか。根拠条文を示しつつ述べなさい。
(解答例)Pの新株予約権の権利行使益の1,000万円と役与員給1,200万円が給与所得の収入金額とされ(所得税法36条1項,2項),給与所得控除額195万円を控除した2,005万円が給与所得の金額となる(同法28条1項,2項,3項五号)。Pには他に収入がないため,総所得金額に算入すべき金額は、2,005万円である(同法22条2項一号)。
(コメント)繰り返し出題されているストックオプションの問題で、個人側の取扱いが問われています。租税特別措置法は適用外である旨が明記されていることと、権利行使が付与決議日から2年内に行われていることから、本ケースは、個人側では非課税とならず、給与所得扱いとなる、税制非適格ストックオプションに該当します。
問2:A~法人税法【非適格ストックオプション~会社側】
問い:事実①のP による新株予約権の行使に関して,A 社において,法人税法上,どのように取り扱われるか。根拠条文を示しつつ述べなさい。
(解答例)Pが新株予約権を行使し、給与等課税事由が生じたため、A社は、令和6事業年度における法人税額の計算上、Pが行使した新株予約権に係る公正な価額を給与手当等として、損金の額に算入する(法人税法54条の2第1項、34条1項二号、22条3項2号)。
(コメント)非適格ストックオプションの会社側の取扱いです。どこの専門学校でも、所得税法などの講義で個人側と会社側の取扱いについて、丁寧な解説を行っているはずなので、しっかりと対応できて欲しい問題です。
問3:B~消費税法【売上に係る対価の返還等】
A 社は,令和6年3月25日,国内において製品甲をB 社に販売するとともに,同日,製品甲を外国法人であるC 社に輸出した。A 社は,令和6年4月10日,製品甲の一部に欠陥が見つかったことから,販売価格(税込)の10%の金額をB 社及びC 社にそれぞれ返還した。A 社は,B 社及びC社に対する上記返還金額の明細を記録した帳簿を保存している。また,A 社が行った輸出取引は,財務省令で定めるところにより証明されたものである(事実②)。
問い:事実②に関して,A 社がB 社及びC 社に返還した金額に係る消費税額は,A 社において,消費税法上,それぞれどのように取り扱われるか。根拠条文を示しつつ述べなさい。なお,課税売上割合については考慮する必要はない。
(解答例)A社はB社に対し国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額のうち、その10%を返還をしていることから,返還した金額に係る消費税額は,令和6事業年度における課税標準額に対する消費税額から控除する(消費税法38条1項)。これに対して,C社への輸出取引は,消費税が免除されているため(同法7条1項),消費税法上の取扱いはない。
(コメント)仕入に係る対価の返還等、売上返還等に係る消費税額の控除については、何故か税理士試験で繰り返し問われている論点です。今回は10%の売上値引きですが、値引き・割戻しは、売上返還等に含められます。国内売上の返還等、輸出売上の返還等、ともに消費税法上の取扱いはご存じの通りで、国内売上の返還等の38条1項はすぐに見つかったはずです。ただ、輸出売上は免税なので、そもそも消費税が課されておらず、返還等について規定している条文がないので、そもそも免税である点を7条1項で指摘するほかないのですが、指摘できなかった受験生が多かったと思います。
問4:B~法人税法【債務免除益】
A 社は,D 社に対して500 万円の未回収の代金債権を有していたが,令和6年11月20日にD社の再生計画認可の決定により,その金額のうち450 万円が切り捨てられた(事実③)。
問い:事実③のA 社がD 社に対して有していた代金債権に関して,A 社及びD 社において,法人税法上,それぞれどのように取り扱われるか。根拠条文を示しつつ述べなさい。
(解答例)D社の再生計画認可の決定により、A社は、未回収の代金債権のうち450万円を切り捨てたため,A社の令和6事業年度における法人税額の計算上、450万円を貸倒損失として、損金の額に算入する(法人税法22条3項三号)。一方、D社は,A社から免除を受けた債務の金額450万円を,債務免除益として令和6事業年度の益金の額に算入する(同法22条2項)。
(コメント)条文が見つからない、時間がない・・・。困ったときの22条ですが、受験生にとって、個別具体的な条文がない問題は解きにくいですね。
問題2:
問1:C~法人税法【リース貸し手/延払基準】
記述①:B社の令和5事業年度の法人税額の計算上,C社から受領した3億9,000万円のリース料のうち,延払基準の方法によって経理した3億6,000万円は,益金の額に算入される。
(正誤判定)×
(解答例)A社の令和5事業年度の法人税額の計算上,リース料として受領した3億9,000万円が益金の額に算入される(法人税法63条1項,64条の2第3項)。
(コメント)延払基準の方法は、令和7年度の税制改正で廃止されることが周知されていたため、大手専門学校でも取扱いをやめていた論点です。今後の出題も見込めないため、復習は不要です。
問2:C~消費税法【リース貸し手/延払基準】
記述②:B社がC 社から令和6年3月20日に受領した3,000万円は,B社の消費税額の計算上,令和5課税期間の課税標準の額に含まれる。
(正誤判定)○
(解答例)消費税法16条1項、28条1項
(コメント)問1と同様、復習は不要です。
問3:A~法人税法【受取配当/非支配目的株式】
記述③:A 社の令和6事業年度の法人税額の計算上,B 社から受領した1,000万円の剰余金の配当は,益金の額に算入されない。
(正誤判定)×
(解答例)A 社の令和6事業年度の法人税額の計算上,B 社から受領した剰余金の配当1,000万円のうち、800万円は益金の額に算入され、200万円は益金の額に算入されない(法人税法23条1項1号,6項)。
(コメント)B社株式の保有割合は5%なので、B社株式は「非支配目的株式等」に分類されます。
問4:B~所得税法【非居住者の所得に係る源泉徴収】
記述④:A社は,Pへの剰余金の配当の支払について,20万円の源泉所得税を徴収し,納付する義務を負う。
(正誤判定)○
(解答例)所得税法161条1項9号イ、212条1項,213条1項1号
(コメント)所得税法の学習に投下できる時間が限られる中、非居住者へ支払う剰余金の配当の「源泉徴収所得税の税率」まで要求するのは酷な気かがします。ただ、答練で、非居住者に土地を譲渡したときの源泉徴収所得税について、所得税法161条1項5号、212条1項、213条1項2号を論拠とする問題を出題しておいたので、解いていた方はできたと思います。
問5:B~法人税法【隠蔽仮装行為にかかる費用】
記述⑤:B社の令和6事業年度の法人税額の計算上,B社の架空の費用及びQに対する手数料200万円は,損金の額に算入されない。
(正誤判定)○
(解答例)法人税法22条3項,4項、55条1項
(コメント)隠蔽仮装に協力したQに対する手数料が損金の額に算入されない、という55条1項については知っている受験生が多いはずです。55条1項が指摘できていれば、大丈夫です。もう一方の、「架空の費用が『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算』されたものではないので、架空の費用が損金の額に算入されない。」というロジック、つまり、22条3項、4項を根拠条文とするのは、税理士試験で先人たちか培ってきた知恵ですが、初見では思いつかないので、こちらは、指摘できなかったとしても大丈夫です。
第2問:計算(60点)
問題1と問題2が法人税法、問題3が所得税法、問題4と問題5は消費税法という構成でした。
解答箇所数は、法人税法15箇所、所得税法7箇所、消費税法8箇所なので、配点は、法人税法30点、所得税法14点、消費税法16点です。学習時間の目安にして下さい。
正答してほしいのが、法人税法が 8箇所/15箇所、所得税法が 3箇所/7箇所、消費税法が 6箇所/8箇所で、全体では17箇所/30箇所(57%)程度が合格ラインと予想しています。
問題1:法人税法(総合問題)
問題1の解答箇所13箇所で、Aランクは 5箇所、Bランクは 3箇所、Cランクは 5箇所です。Aランクをすべて正答し、Bランクの問題の半分を正答すれば、合格ラインに到達できるので、ここでは、AランクとBランクの問題のみを解説します。
問1:所得金額の計算
(1) 租税公課に関する申告調整:A×3箇所
資料の与えられ方が複雑で、一見して難解のようにも感じられますが、租税公課は定型的に解ける下書きの作成方法があります。租税公課の過去問も全てその下書きにあてはめれば解くことができますが、ここでは詳細を割愛し、簡単な解説にとどめます。
1. 前期末未払法人税等について
申告時に損金算入できる事業税を損金経理していません。∴ 13,201,900円(減算)
2. 中間納付、及び期末未払計上分について
損金算入できない中間納付分の法人税及び地方法人税 46,980,400円と住民税 4,672,100円、損金算入できない期末未払計上分 50,407,800円、及び損金算入できない源泉所得税等 673,860円の合計 102,734,160円が損金経理されています。
∴ 102,734,160円(加算)
3. 延滞税等について
損金算入できない延滞税及び延滞金 12,000円、印紙税の過怠税 210,000円、及び交通反則金 30,000円の合計 252,000円が損金経理されています。∴ 252,000円(加算)
(2) 受取配当等及び預金利子に関する申告調整:B×1箇所
① 完全子法人株式等(100%) A社株式 300万円
② 関連法人株式等(1/3超100%未満) C社株式 180万円-控除負債利子5万円(∵配当180万×4% > 負債利子50万×10%)= 175万円
③ その他の株式等(5%超1/3以下)
④ 非支配目的株式等(5%以下、特定投信)B社株式 80万円×20%= 16万円
∴ ①+②+④ = 4,910,000円(減算)
(3) 固定資産に関する申告調整:C×1箇所
(4) 退職給付引当金に関する申告調整:C×1箇所
(5) 資産除去債務に関する申告調整:C×1箇所
(6) 交際費等に関する申告調整:B×1箇所
1. 支出交際費等のうち、1万円/人超の接待飲食費(50%損金算入可)
① 接待飲食費450万円-1万円/人以下の飲食費230万円(全額損金算入可)= 220万円
② 新社屋落成式の費用のうち、得意先に供与された飲食費用(1万円超/人) 75万円
①+②= 295万円
2. 支出交際費等のうち、接待飲食費以外(損金不算入)
① 中元歳暮の贈答費用 380万円
② 新社屋落成式の費用のうち、記念品代 24万円
③ ゴルフプレー代 160万円及び年会費4万円
④ 社内飲食費 12万円
①+②+③+④= 580万円
3. 損金不算入額
支出交際費等の額(1.接待飲食費 295万円 + 2.接待飲食費以外の支出交際費等 580万円) - 接待飲食費 295万円×50% = 7,275,000円(加算)
(7) 貸倒れに関する申告調整:B×1箇所
① 法的債権の消滅については、法人の経理にかかわらず、切捨額を損金の額に算入します。
∴ 貸倒損失認定損 800万円(減算)
② 破産手続き開始の申立てによる個別貸倒引当金は、中小法人等のみ繰入可能です。
∴ 貸倒引当金繰入額否認 600万円(加算)
③ ① + ② = 2,000,000円(減算)
問2:法人税額の計算:A×2箇所
甲株式会社は資本金1億円超なので、軽減税率15%は適用されません。所得金額や税率が与えられているので、千円未満切捨後、税率23.2%を乗じるだけです。なお、源泉所得税等の額は、受取配当等の資料を見に行く必要がありますが、百円未満を切捨てるタイミングも与えられていたので、2問とも正答必須の問題です。
① 法人税額 = 所得金額337,041,000円(千円未満切捨)×23.2%= 法人税額 78,193,512円
② 法人税額 78,193,512円 - 源泉所得税等の額[資料]5より 673,860円 = 差引所得に対する法人税額 77,519,600円(百円未満切捨)
∴ 差引確定法人税額 = 77,519,600円 - 中間申告分の法人税額 42,553,300円 = 34,966,300円
問3:利益積立金額の計算:C×2箇所
問題2:法人税法(個別問題)
AランクとBランクの問題がそれぞれ1問ずつ出題されています。
(1) 固定資産に関する申告調整:A×1箇所
100%子会社へ機械装置を時価で譲渡しています。売却益の取消しと減価償却費の調整ですね。取得原価35,000,000円のときの償却限度額が資料に与えられているので、その金額を利用すれば、取得原価26,480,000円のときの償却限度額もすぐに計算できます。
売却益8,520,000円-減価償却費(5,005,000円-5,005,000円×26,480,000/35,000,000)= 7,301,640円(減算)
(2) 寄附金に関する申告調整:B×1箇所
100%子会社への金銭債権600万円を理由もなく放棄したので、子会社に対する寄附金として取り扱うことになります。特定寄付金がなく、損金算入限度額の計算に使用する所得が資料に与えられているので、寄附金等の損金不算入額の計算としては解きやすい問題ですが、捨てている受験生もいるため、Bランクとしておきます。
① 指定寄附金等(I市への寄附金)200万円
② その他の寄附金 150万円
③ 完全支配子会社への寄附金 600万円
④ 合計950万円
一般寄付金の損金算入限度額 ={期末資本金等120,000,000×12/12×2.5/1,000 + 限度額の計算に使用する所得(資料)38,000,000円×2.5/100}× 1/4 = 312,500円
∴ 損金不算入額 = ④9,500,000円-指定2,000,000円-特定0円-一般寄付金の限度額312,500円= 7,187,500円(加算)
問題3:所得税法
解説動画を公表予定です。
問題4・5:所得税法
解説動画を公表予定です。