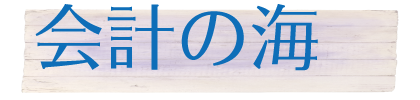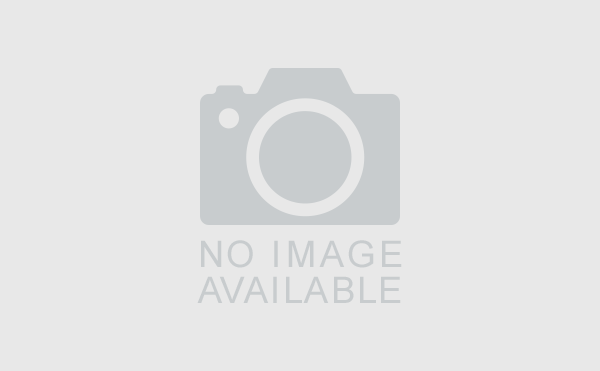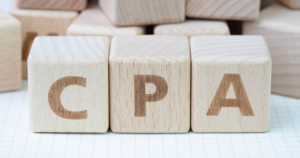【企業法】令和7年公認会計士 論文式試験 講評
本試験、お疲れ様でした。
今回は、企業法の講評です。
第1問:新株発行無効の訴え
新株式の有利発行があった場合の事例問題です。前提条件を明確にした上で、解答しやすいように誘導してくれていて、問題1と問題2は易しかった印象です。ただ、問題3は、問題1と論点を切り替える必要があり、答案構成に苦労したのではないか、と思います。
問題1:有利発行を行う場合に必要となる手続き
「特定の株主に対してのみ、有利な価額で新株を発行する場合に、会社がとるべき会社法上の手続き」を答える問題です。
公開会社の募集事項の決定は、原則として、取締役会が行いますが、有利発行の場合は、公開会社であっても、「有利発行をする理由を株主総会で取締役が説明した上で、株主総会の特別決議により募集事項を決定する。」という手続きが必要となります(201条1項、199条2項3項、309条2項5号)。
ただ、必要となる手続きを記述しただけでは、答案として行数が足りません。作問者は、もう少し何か書いて欲しくて、答案スペースを用意しているはずです。
こういった場合は、上記手続きが必要とされる趣旨や、適用要件へのあてはめ、それでもスペースが埋まらない場合は、本ケースでは不要とされる手続きを列挙して行数を稼ぎます。
「取締役の説明や株主総会の特別決議」が必要とされる趣旨は、既存株主の利益の保護です。
適用要件への当てはめは、本事例が有利発行に該当するかの検討です。
また、本ケースでは、総株式の引受けを行う契約が締結されているため、申込みと割当ての手続きは不要となります(205条1項)。
問題2:新株発行の効力を否定するための「訴えの名称」と条文番号
「新株発行無効の訴え」ですね。
「8/21時点で、株主Eが提起すべき訴え」が問われていますが、7/8に払込済みなので、会社を被告とする「発行差止請求の訴え」を提起することはできないですし、「新株発行の実態がない」という状況ではないので、「新株発行の不存在確認の訴え」でもないですね。
あと、留意点として、本問では、「当該訴えの根拠となる会社法の条文の番号(必要に応じて項番号,号番号及び記号)として最も適切なものを明示して答えなさい。」とされています。一般に、「最も適切なもの」と指示されたら、関連する複数の条文から1つだけを選択して答えます。
ただ、受験校3校の模範解答を拝見しましたが、2校が「828条1項2号、同条2項2号」として、1校が「828条1項2号」としています。
1つに絞れるのであれば1つだけ解答しますが、1つに絞りきれないのであれば、「『複数解答もあり』という風土を作っていこう。」ということでしょう。
問題3:新株発行の効力を否定するために主張すべき内容
「新株発行の無効の訴えに基づき、新株発行の効力を否定するために、株主Eは、どのような主張をすべきか、判例の趣旨を踏まえて答えなさい。」という問題でした。
新株発行無効の訴えに係る無効事由については、明文規定がないため、解釈にゆだねられます。
一般的には、「新株発行にあたり遵守すべき法令又は定款の規定に違反した場合には、その新株発行の無効事由になる。」と考えることもできますが、新株発行後に無効とすると、「新株主や第三者に不測の損害を与えてしまうおそれがあり、取引の安全性を害する危険がある。」と考えることもできます。
そこで、ケースごとに両者を比較衡量して判断することになりますが、判例では、下表のようにケースごとに異なる結論を出しています。
| 無効事由となるケース | 無効事由とはならないケース |
| ①. 公開会社における、募集事項の通知・公告を欠く募集株式の発行 | ②. 公開会社における、株主総会の特別決議を欠く第三者への有利発行 |
| ③. 発行可能株式総数を超えるような重大な法令違反がある株式の発行 | ④. 公開会社における、取締役会決議を欠く募集株式の発行 |
| ⑤. 新株発行の差止請求を無視して行われた株式の発行 | ⑥. 著しく不公正な方法による新株の発行 |
本問に関連する判例は、上表①と②です。
株主Eは、上表①を理由に新株発行が無効であることを主張すれば、その主張は認められます。
ところが、上表②を理由に無効を主張すると、残念ながら株主Eの主張は認められないことになります。
本問では、「新株発行の効力を否定するために、Eがどのような結論をすべきか?」が問われているので、結論が無効事由となるように、上表①を選択して、答案を作成する必要があります。
問題1は上表②を論点としているので、その流れで、問題3でも上表②をベースに「株主Eの主張」を解答した受験生も多いはずです。
ただ、作問者は、上表①をベースに答案を作成して貰いたいようで、問題文の後半に「Bは,これをもって本件発行の手続は適法に行われたと考え,甲会社株主に対して,本件発行に係る募集事項の通知又は公告をしなかった。」として、「本問の論点は公示欠缺」というヒントを与えてくれています。それでも、問題3の段階で、上表②から上表①に論点を切り替えて答案を作成するのは、難しかったはずです。
受験校3校の解説動画を拝見しましたが、3校とも、「上表①の公示欠缺」をベースに模範解答を作成していて、しかも、本事例が「例外的に公示欠缺とならない場合には該当しない」という付加的な論点にまで言及していました。
問題3に対して「難しい」という感想を正直に語られていたのは、最も人気のある受験校の講師だけでした。人気があるのもうなずけます。
第2問:監査等委員会設置会社の役員の報酬等
答案の用意があるであろうメジャーな論点からの出題でしたから、迷わず書き進められたのではないでしょうか。「最高裁判所の判例の趣旨に基づいて」「最高裁判所の判例によれば」といった指示が問題文中にありますが、受験生が講義で学習するのは基本的に判例に基づくので、臆することなく自身の知識を披露してください。
問題1:取締役の報酬等の決定に関する株主総会における意見陳述権
① 監査等委員である取締役の報酬等に関する意見陳述権(361条5項)は、各監査等委員の権限で有り、監査等委員である取締役の地位の独立性の確保を趣旨とします。
② 監査等委員以外の取締役の報酬等に関する意見陳述権(361条6項)は、監査等委員会が選定する監査等委員の権限で有り、監査等委員会の監督機能の実効性の確保を趣旨とします。
①は監査する側の報酬等であり②は監査される側の報酬等であると考えると分かり易いですね。
問題2:使用人兼務取締役の使用人としての給与と取締役の報酬規定
「Aに対する部長職分の給与の支払は会社法上の報酬規制の潜脱になるか」と問題文中に問題提起までされているので、論点ずれを起こしようもない問題となっています。報酬規制(361条1項)はお手盛り防止を趣旨とするため、①報酬規制は取締役としての職務執行の対価としての報酬等を対象とすること、②使用人の給与体系が確立し、その給与体系に基づく支給である限りお手盛りの弊害はないこと、この2点を根拠に報酬規制の潜脱には当たらないと論じます。
問題3:退職慰労金と取締役の報酬規定
(1)退職慰労金が報酬規制の対象となるかは、退職慰労金の決定においてお手盛りの弊害が生じるかいなかで判断します。①退職慰労金の在職中の職務執行の対価の後払いとしての性格、②後に退任する現職取締役の退職慰労金への影響からお手盛りの弊害が認められるため、報酬規制の対象となる報酬等に当たると論じます。
(2)退職慰労金の一任決議の効力もお手盛りの弊害が生じるかいなかで判断します。①一定の基準による決定が確立している又は確立している、②基準の存在を株主が知りうる、③①の基準の範囲内で決定する決議である、ならば実質的にお手盛りの弊害が生じないとし、一任決議は可能です。本問の場合、③議案として上程された①退職慰労金の支給基準が②株主総会参考資料に記載されているため、一任決議の効力ありと論じます。